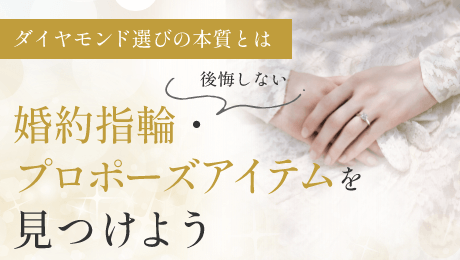婚姻届のもらい方は?提出先や婚姻届提出に必要な手順を解説

彼とふたりでする最初の共同作業とも言われている「婚姻届の提出」は、とても楽しみで、意味のあるものですよね。
しかし、「SNSなどで見る可愛いものがほしい!」「土日は?」「おしゃれな婚姻届は役所でももらえる?」「役所に行く時間がないけどどこかでもらえる場所はある?」など様々な疑問が浮かびます。
ここでは、婚姻届に関する疑問や、提出の際の手順などをご紹介・解説していきます。
2023年08月23日更新
Contents
婚姻届はどこで手に入る?
「婚姻届をもらうのは役所で」というのは一般的に広がっていますが、働き方も様々で、男女関係なく多忙なこの時代。
またふたりでの予定が合わずに営業時間や開庁時間である8:00〜17:00の間に「役所に行けない」なんてこともあります。
そのため現在では大きく分けて4つの婚姻届のもらい方があります。
ここでは、婚姻届けをもらう際の場所や方法をご紹介します。
役所でもらう
もっとも一般的なのが、区役所などの窓口でもらうこと。
区役所や区役所市民課などでもらうことができる婚姻届は、可愛らしいものなどではなくごく一般的でシンプルなデザインです。婚姻届事態は「もらう(入手)だけ」であれば、どの管轄や区役所などでも可能なため、こだわりがなければ「何かのついでにもらってくる」こともできます。
ご当地婚姻届などが欲しい場合は、その地域に旅行に行った際にもらってくるのも良いでしょう。
また、地域や区によっては、窓口に声をかけてもらわなくてもラックや、婚姻届配布ブースなどが設けられている場合があります。
ただし、区や地域によって婚姻届を管理している課が「市民課」「別受付窓口」など、市区町村によって違いがあるので注意しましょう。
配布サイトでダウンロードする
「婚姻届は可愛いものにしたい」と考える人も増えている近年ではSNSで見る可愛い婚姻届や、書類デザインを配布しているサイトがあります。
配布サイトでお気に入りのデザインをダウンロードし、プリントすることで使用できます。
婚姻届は、規定が守られていればどのようなデザインでも入籍のための手続きとして有効です。
可愛らしいデザインや少し変わったもの、コラボした婚姻届なども無料でダウンロードできるサイトも増えています。
また、ものによっては提出用・予備用・保存用などもありふたりの思い出として手元に残しておくのも良いかもしれません。
近年では、人気キャラクターやブランド、モデル・アーティストなどがコラボした婚姻届などもあり、多種多様なものから選ぶことができます。
コンビニのマルチコピー機でプリントする
各種コンビニのマルチコピー機では、婚姻届をプリントすることができる場合があります。
各社によって登録されているデザインは異なるので、公式サイトなどから事前に確認しておくことをおすすめします。
一般的な婚姻届も自治体のHPからダウンロードでき、オリジナルやデザインが可愛いものもダウンロードできますが、お家にプリンターがない場合も多くパソコンではなくスマホの人も多い時代です。
PDFデータがあればコンビニでプリントすることで、婚姻届が手に入ります。時間を制限されないため、ふたりでコンビニに行ってプリントするのも良いでしょう。
また、コンビニ印刷であれば料金は、80〜150円程度です。
オリジナルデザインをオーダーする
婚姻届をオリジナルでデザインするサービスもあります。
提出用だけではなく保存用としてもおすすめです。
婚姻届は、基本のルールが守られていれば、どのようなデザインでも提出・受理が可能なため、近年ではふたりの共通の趣味や馴れ初めなどに合ったオリジナルのデザインをオーダーしてオリジナル婚姻届を出すカップルも増えてきています。
オリジナル婚姻届を作る際のルールや注意点は以下のようなものがあり、記載ミスなどがあると婚姻届書として扱われません。
①印刷はA3サイズの長方形用紙
②用紙種類は、一般的なコピー用紙(普通紙)もしくは上質紙
③規定の情報・項目は必ず入れる
④切り込み・変形・シールなどの装飾は不可
婚姻届について気を付けるポイント
婚姻届を提出する場合、書き間違いなど記入の不備に注意が必要です。
記入ミス・署名押印ミスなどがあると内容の確認や修正を行う必要があり、受理に時間がかかる場合も。
証人欄に不備があった場合はその場で受理してもらうことができない可能性もあります。
記入の際は実例や見本、記載例を見ながら書くと良いでしょう。
また、戸籍謄本など受理に必要な書類の添付忘れ、きえるボールペンの使用なども受理できない対象となります。
時間外受付で提出する場合はその場で確認してもらうことができないため、何回もチェックや確認をして不備のないようにしましょう。
入籍日にこだわりがある場合などは事前に窓口で内容の確認をしてもらい、改めて入籍したい日に提出するようにすると安心です。
婚姻届の提出に必要な準備
婚姻届をもらってきたら、いよいよ記入と提出へ向けて動き出しましょう。
婚姻届を提出する際は、婚姻届そのものだけではなく他にも必要書類があります。
中に戸籍謄本などもあるため、婚姻届をダウンロードした後に、必要書類を先にもらっておくと婚姻届に書く際もスムーズです。
ここでは、婚姻届の提出に必要な準備を婚姻届の記入からご紹介します。
婚姻届に必要事項を記入
婚姻届に必要事項を記入します。
代理人などではなく、届出人本人が見本やすでに描かれているものを見ながら記入していきましょう。
ありがちなミスとして、「番地違い」「旧姓漢字の間違い」「本籍地の番地や場所が違う」などがあるため、戸籍謄本などの必要書類が全て揃ってから書き始めると良いでしょう。
婚姻届には父母の名前を記入しますが、亡くなっている場合や離婚している場合も記入は必要です。
基本的な記入事項は以下の通りです。
・届出日・届出先
・氏名・生年月日
・住所
・本籍
・父母の氏名・父母との続き柄
・婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
・同居を始めたとき・初婚・再婚の別
・同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業
・届出人
・証人
・連絡先
記入内容に不備があった場合、役所から連絡が来ます。
確実に連絡が取れる電話番号を連絡先には記入するようにしましょう。
消えるボールペンや、鉛筆などは受理対象ではないので注意が必要です。
証人欄への署名
婚姻届を受理してもらうためには、ふたりが選んだ証人の署名と押印が必要です。
これは「ふたりが結婚・入籍することを認めます。見届けます。」という意味を持ち、偽装結婚・未承認やどちらかに無断での婚姻届が提出されてしまうことを防ぐ役割を持っています。
ただし、2021年(令和3年)9月から戸籍の届書への押印義務が廃止され、婚姻届の押印は任意になっています。
記念に押印したい人や、年齢が高い場合は押印をすることを大事にしている人もいるため任意とはいえ考慮しておきましょう。
書き方は、氏名・生年月日・住所・本籍・押印(認印、実印)を記入するだけ。
ただし、押印はゴム印やシャチハタは不可となるので注意しましょう。
戸籍謄本もしくは戸籍抄本
戸籍の内容をすべて写した証明書が「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」この戸籍謄本の中から、必要な個人の分だけを写したものを「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」といいます。
戸籍課や戸籍担当の課で取り寄せをしましょう。
本籍地と届け出る役所が違う場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になる場合があります。
また、自分が覚えている住所と、戸籍謄本上の住所が違う(略称や番地)場合もあるので、取り寄せ正しい情報を記入すると安心でしょう。
婚姻届の提出先が、本籍地のある市区町村と同じ場合は戸籍謄本の提出は必要ありません。
ふたりの旧姓の印鑑
婚姻届に押印する印鑑は、ふたりの旧姓の印鑑です。
婚姻届を出す時点ではまだ同じ姓としての状態ではないため「これから結婚するという届出」になります。
そのため、結婚後・婚姻後の苗字が旧姓とかわらない場合であっても別々の印鑑が必要となります。
また、旧姓印鑑は証人と同じくゴム印やシャチハタは不可となるので注意しましょう。
押印ミスをしたときは、ほとんどの公的書類と同じように二重線を引いた後、欄内の余白に正しい内容を書くことで有効となります。
父母の同意書(未成年の場合)
成人年齢が変化しましたが、男性、女性ともに18歳から父母の同意なく婚姻の届出をすることができます。
また、令和4年4月1日時点で16歳以上だった女性は18歳未満でも婚姻可能です。
ただし、16歳は未成年なため本人確認などと同時に父母の同意が必要となります。
また、別紙での同意書ではなくても婚姻届の証人欄に両親が署名している場合は同意書としての扱いです。
届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してある場合も有効とされることがあります。
よくある質問や問い合わせで提出先の役所などに確認しておくと間違いがなくて良いでしょう。
婚姻届の提出先
必要事項を記入し、書類などの用意と不備がないことを確認が終われば、いよいよ提出です。
提出時には、本人確認書類や、必要書類を準備し、提出しましょう。
開庁日以外でも提出は可能で、休日や夜間にも出張所や休日夜間窓口などとして空いているところがあります。
提出は日本のどこの役所でもOK
婚姻届の提出は、どの自治体でもできます。
ただし、注意点として本籍地以外の役所に提出する場合は、それぞれの戸籍謄本が必要になります。
【本籍地位以外での提出例】
・ディズニー好同士なので舞浜で
・出会った旅行先で
・憧れの地域や将来住みたい地域で
・どちらかの地元や住所のある場所で
など。
地域によっては、婚姻届に関するサービスが充実している自治体やフォトブースが用意してあり、そこまで赴いて提出するカップルも少なくありません。
提出した時点で婚姻成立となり、晴れて戸籍上でも夫婦となります。
また、提出の際には必ず本人確認が必要となり、法律で義務付けられています。
証明書によっては、1枚もしくは2枚以上の提示が必要です。
【1枚の提示で良い本人確認の証明書例】
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
・身体障害者手帳
【2枚以上必要な本人確認の証明書例】
・写真が貼られていないマイナンバーの通知カード
・国民健康保険、健康保険などの被保険者証
・国民年金手帳
また、婚姻後、戸籍ができるまでは少し時間がかかり、その間に会社などで戸籍謄本などが必要になった際に使える「婚姻届受理証明書」をもらっておくと良いでしょう。
戸籍謄本の代わりとして提出でき、手続きを進めることができます。
書類タイプや賞状タイプがあります。
夜間・休日に提出する場合
お仕事などの関係で、夜間や休日以外に時間を取れない人も少なくありません。
婚姻届は、夜間や休日窓口にも時間外提出をすることができます。
ただし、出張窓口などになるため、その場で内容確認をしてもらえるわけではなく書類記入に不備があると後日修正依頼などの電話が来てしまい、提出日・届出日と、実際の婚姻日・入籍日がずれてしまう可能性があるので注意しましょう。
また、区によって夜間休日の提出について「よくある質問」にまとめられていることがあるので提出したい地域のものを確認してみましょう。
婚姻届は2人で最初の共同作業
多くの人の前でする結婚式は実感が湧きやすいですが婚姻届の提出は以外にもあっさりとした手続きです。
しかし、そのあっさりした手続きはふたりでする最初の共同作業。
ふたりのこれからを戸籍上、日本の法律上保証するものでもあります。
婚姻届をだした日から、ふたりの未来がさらに始まるのです。
せっかく色々考えて出したのに、不備や確認不足で入籍日がずれてしまうのは切ないので間違いがないように、慎重に準備しましょう。
わからないことや、不明点、不明確な点は問い合わせや調べて、確実に出せるよう準備をしましょう。